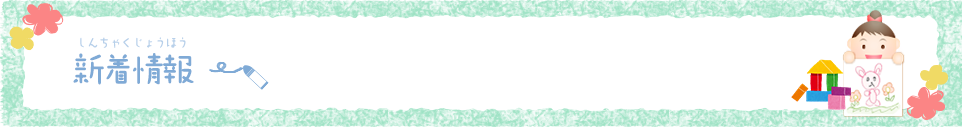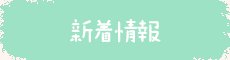お知らせ
これからの保育を創っていく学生たち【大阪健康福祉短期大学の実践演習】
2024.11.27
お姉ちゃん先生・お兄ちゃん先生が来てくれました♪
事前に計画・準備してきた『設定保育』の実践をしてくれる日!!
学生にとって、ドキドキしていたと思いますが・・・
「上手くやろうと思わなくてもいいよ」と最初に伝えました。
大切なのは『学びと気づき』をたくさん見つけることなんです☆
3クラス行ったり来たりしたので、しっかりと実践の中身を見ることや全ての取り組みの写真を撮ることが
できませんでしたが・・・
学生の皆さんが頑張っている姿と子どもたちの楽しそうな表情をお伝えします♪
◎ぱんだ組チーム『カレーライスを作ろう!!』 ※『 』のタイトルはたろうが勝手に考えました(笑)
 |
 |
手遊びや絵本を読み、少しずつ「かれーらいすを つくろう」という気持ちが高まります…
 |
 |
 |
 |
カレーライスに必要な具材を作り、鍋に入れて「カレーライスのうた」の手遊びをしていると完成!!
 |
 |
「おいしい~♪」
みんなで作ったカレーライスは、さぞかし格別な味だったと思います(笑)

環境構成が思っていたことと少し違っていた中で、臨機応変に対応していたことに感心しました。
花紙や新聞紙、折り紙やプチプチ(一般名称は「気泡緩衝材」というようです)など
いろんな素材を使っていたことも、子どもたちの興味関心を広げていったと思います。
何よりも・・・
このチームの学生たちの明るい雰囲気が、子どもたちを「たのしい」気分にさせた要因の一つだと思います☆
◎きりん組チーム『よく噛んで食べよう!!』 ※はい♪『 』のタイトルはたろうが勝手に考えました(笑)


手遊びや絵本を読んで“食べる”“噛む”へ意識が向き始めていきます。
 |
 |

“パクパク”の折り方を一つひとつ丁寧に伝えています。
 |
 |
 |
 |
折り紙が得意な子ども・不得意な子ども…また、発達も一人ひとり違うので
「できへん」「むずかしい」という子どももいたと思いますが・・・
その時の子どもへの援助・配慮などの学びもあったと思います。
一人ひとりに丁寧に関わっている学生の姿も感心しました。
 |
 |

子どもが作った“パクパク”の折り紙を持って歌を歌ったり、事前に用意していた模型「ベルちゃん」を使って
『噛む』ことの大切さを伝えていました。
子どもたちは、楽しみながらその大切さを学べたと思います。

4歳児のこの時期になると、自分の身体に対しての自覚が育まれてくるので
よく噛んで食べることで『どうなるのか?』その意味を伝えることは良かったと思います。
「30回噛む」という具体的な数字を示したのも、子どもの意欲に繋がっていきますね。
今回、折り紙の制作で“一つひとつ作り方”を教えていましたが(今回はそれで良いと思います!)
ここからは参考まで・・・
最初に作り方を“最後まで一通り”教えてから
「さあ、パクパク作ってみよう!」と取り組むことでどうなるか?想像してみましょう♪
「わからへん」「できへん」「どうやったっけ?」という声が、すぐに想定されますが(笑)
作っている友だちを見たり、その友だちに聞いたりすることができるような援助・配慮から
友だちと繋げるような取り組み方もあるかな?と・・・
また『わからへん・できへん時』に“どうしたらいいか?”考える力を育むことにも繋がっていきます☆
◎らいおん組チーム『これを食べたらどうなる?』 ※当然!『 』のタイトルはたろうが勝手に…(笑)
 |
 |
手遊びや絵本から、子どもの意識が学生に向き始めてきています♪
子どもたち…手遊びも楽しそうにしていますね(#^^#)
 |
 |
箱の中の食べ物が何なのか?手で触れながら、グループのみんなで答えを導き出します♪
 |
 |
 |
 |
 |
 |
見事に正解を導き出した後は、選んだ食べ物が三大栄養素のどの項目になるのかを考え
最後は、学生と一緒に確認しました♪
箱の中身が見えないことで「なにかな~?」というような、わくわく感が更に高まっていましたね。
また、5歳児になると段々と知的に考えられるようになり
三大栄養素のことを教えてもらうことで、自分の生活を更に良くしていこうとする意識に繋がると思います。
ここからは参考まで・・・
食材をその場で切り、その断面図を見たり、食材のにおいを嗅いだり・・・
そして、そのまま食べられる物ならば、かじったり(笑)
『五感』を使って“食”の興味関心を更に高めるような遊びも考えられるかな?と思います(#^^#)
◎現場の保育教諭からのアドバイスも学びに・・・
 |
 |
現場の保育教諭からの意見を聞くことも大切な学びになると思います。
また、伝える側としても学生から学ばせてもらえる良い機会になるんです♪
ちなみに・・・
アドバイスを送った保育教諭たちは、大阪健康福祉短期大学の卒業生!!
皆さんも、現場で実践を積み重ねていき、このようにしっかり伝える側になっていきましょう☆
今回の『設定保育』を通して、良かった点・改善すべき点を各グループで考察・共有し合い
現場に立った時の実践力につなげて欲しいと思います。
そして・・・
「子どもたちの為に、仕事をしたい!」という気持ちが更に強くなってくれていたら嬉しいです♪
未来を担う子どもたちの為に
これからの保育を一緒に創っていきましょう☆